
本書のポイント
1、砲の命中率とは、ハードやそれの訓練だけでは簡単に得られない。つまり砲術計算というソフトが死命を制する。日露戦争全期間を通じて、日本の命中率がロシアを常に上回っていたのは、砲手の訓練だったり、大和民族が優秀であったりしたわけではない。日本の砲術というソフト技術がすぐれていたのだ。
2、日本側は主力艦隊を遊撃隊と本隊とに分け、両方ともに単縦陣とし、相互に協力して戦おうとした。理由は本隊の低速のためである。しかしながら、高速部隊を本隊から独立させて、別個の指揮のもと運用するという考え方は、きわめて斬新であり、以降の海軍戦術で主流をなす方法となった。
3、敵前大回頭は、司馬遼太郎=黛治夫の言うように「弾が当たらないこと」を、英知をもって計算して実行したものではない。東郷司令部は、これがT字の理想であり、「弾が当たること」を、覚悟して実行した。
目 次
第1章 近代戦艦の歴史 9
司馬は「海戦は戦艦で決定される」と考えた 9
リサ海戦―衝角戦術による勝利 13
鉄の心をもつ提督、テゲトフ 20
大口径砲搭載のイタリア型砲艦 21
大口径砲より有利な六インチ速射砲 25
万能艦として期待された六インチ巡洋艦 27
マカロフの六インチ巡洋艦無敵論 29
巨大戦艦イタリアの衝撃 33
近代戦艦の祖、マジェスティックの出現 34
その後の戦艦設計の主流となった三笠 38
ロシアの主力戦艦ボロジノ級の重大な欠陥 42第2章 日清戦争の黄海海戦 46
中口径速射砲を重視した日本海軍 46
艦の速度によって艦隊を分ける 48
単縦陣対横陣の黄海海戦 50
巡洋艦が戦艦に勝った 56第3章 砲術の進歩 59
数学の能力を問われる砲術将校 59
砲術の基本―左右を照準する 63
砲術の基本―前後の識別をつける 67
砲術計算というソフトが死命を制する 72
照準望遠鏡・測距儀・トランスミッター 74
第4章 日本人だけが認めたマハンの海軍戦略 77
歴史学的には疑問の多いマハンの海上権力論 77
通商破壊戦を嫌ったマハンの艦隊決戦論 80
古ぼけたマハンの将校教育論 86
マハンの日露戦争の評論 88第5章 米西戦争 91
戦艦メイン爆沈の謎 91
米艦隊の一方的勝利だったマニラ湾海戦 96
サンチャゴ・デ・キューバ海戦における索敵活動 105
サンチャゴ・デ・キューバ海戦と閉塞作戦 111
なんと戦艦が巡洋艦より速かった 116
第6章 東郷平八郎 120
出 生 120
「艦砲とはなかなか当たらないものだ」 121
「黒田清隆の慧眼に敬服した」 123
イギリス留学で学んだこと 126
袁世凱の言論にいっさい耳を貸さず 128
ハワイ王朝崩壊と邦人保護事件 130
戦時国際法にのっとった高陞号撃沈 133
なぜ東郷が連合艦隊司令長官に選ばれたか 139
東郷平八郎と条約派 144第7章 日露両海軍の戦略 149
ロシアの最高の人材を海軍に投入した 149
遅れたバルチック艦隊の出師準備発動 152
マカロフの艦隊温存策 155
近接封鎖と閉塞作戦はなぜ失敗したか 158
砲術の権威、ロジェストウェンスキー 162
仮装巡洋艦ウェスタの勝利 164
第一回目の極東回航 166
激賞された砲術練習艦隊の演習 170第8章 機雷を初めて攻撃につかう 173
マカロフ理論とヒョロヒョロ魚雷 173
敵味方を区別しない機械水雷 179
世界で初めて機雷で戦艦を撃沈した男 182
連繋水雷 187第9章 旅順艦隊の全滅 190
東郷暗殺計画 190
永野修身の一二〇ミリ砲弾 193
黄海海戦―一万メートルの砲戦 196
なぜ、旅順艦隊は敗れたか 204第10章 バルチック艦隊の東征 211
ニコライ二世と日本海海戦 211
バルチック艦隊の東征と旅順艦隊全滅 214
ロジェストウェンスキーの本意 218
クロンシュタット出港 222
ドッガー・バンク事件 225
フランスは外交戦略の転換を決意した 231
困難をきわめたアフリカ周回 233
囮となったフェルケルザム分遣隊 235
遅れたドブロトワルスキー分遣隊 238
第三太平洋艦隊の結成 240
「貴官の任務は日本海の制海権を得ることにある」 245
ロジェストウェンスキー最後の決断 247
マラッカ海峡の白昼通過 252
「バルチック艦隊も旅順艦隊の二の舞になる」 256
ネボガトフ艦隊との再会 259
ウラジオへの三つの針路と石炭補給 261
津軽海峡封鎖作戦 266
連合艦隊、動かず 268第11章 日本海海戦 275
ロジェストウェンスキーの決心 275
東郷平八郎の決心 278
反航戦からT字をきる戦法を発見せねばならなかった 283
単縦陣、そして連繋機雷 287
「敵艦見ゆ」 291
敵前大回頭 294
ロジェストウェンスキー昏倒 302
なぜZ字戦法はなかったか? 303
魔の二八発目 305
戦艦オスラビアの最期 309
戦艦スワロフ・アレクサンダー三世・ボロジノの最期 313
戦艦シソイ・ナワーリンの最期 320
ネボガトフの降伏 324第12章 エピローグ 328
ペテルブルグへの悲報 328
捕虜の送還 331
軍法会議 335 主要参考文献 340
あとがき 344
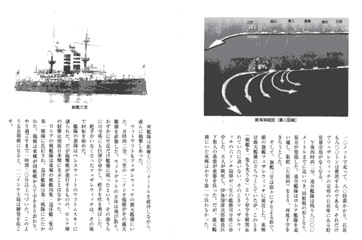 あとがき
あとがき